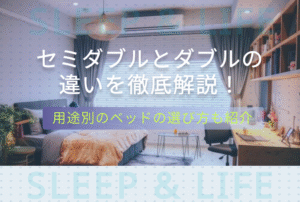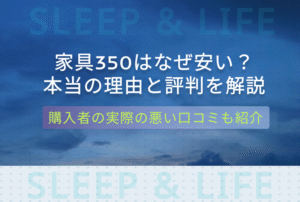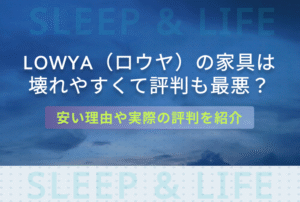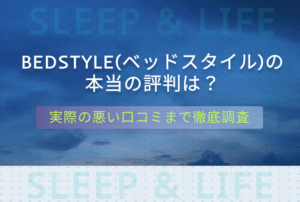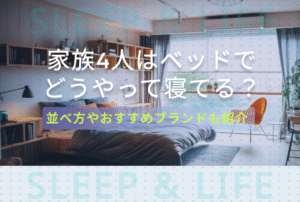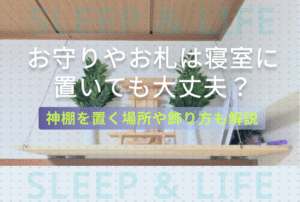睡眠時、寝返りを打つたびに「ギシギシ」「ミシミシ」と聞こえるベッドの軋む音が気になる人もいますよね。集合住宅や賃貸物件に住んでいる場合、音漏れなども心配になるかもしれません。
本記事では、そんな悩みを解消するために、軋む原因や対策、軋まないベッドの選び方やおすすめブランドを紹介します。また、軋むベッドの正しいメンテナンス方法も解説。
静かで快適な睡眠環境を手に入れたい人は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
ベッドが軋む4つの主な原因と対策

ベッドが軋む原因は、ひとつではありません。複数の要因が重なって音が発生するケースがあります。
- 床との摩擦
- ベッドフレームの歪み
- マットレスのコイル劣化
- 金具の緩み
まずは原因を把握しましょう。
原因① 床との摩擦

ひとつめの原因は、ベッドの脚と床の間に摩擦が生じ、床に傷や軋み音が発生するケースです。フローリングなど滑りやすい床材では、少しの揺れでも音につながることがあります。摩擦のたびに床材が擦れ、ベッドの振動が音として反響するのが理由です。
対策方法は、 ベッド下にカーペットや防音マット、ベッド音防止シートを敷くと摩擦音を軽減できます。床の保護にもなり、インテリアとしても機能するのでおすすめです。
原因② ベッドフレームの歪み

ふたつめの原因は、ベッドフレームの歪みです。長年の使用や重みによってフレームが歪むと、接合部分に負荷がかかり軋みの原因になります。とくに高さのあるベッドや耐荷重が小さい商品は注意が必要です。
目視で歪みやたわみが確認できる場合は、フレームに負荷がかかっている可能性があります。ひび割れなどがみつかった際は、すぐに交換や買い替えを検討しましょう。
対策は、耐久性の高いベッドに買い替えたり、補強材を使って安定性を高めたりすることです。補強金具や耐震パーツを使うのも効果的でしょう。
▼頑丈なベッドについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
原因③ マットレスのコイル劣化

マットレスにスプリング(コイル)が入っている商品は、経年劣化でバネがきしみやすくなります。内部の金属がさびついたり、ヘタってきたりすると、ちょっとした動きでもギシギシと音を立てやすいです。
コイルの音が気になる場合は、ノンコイル(ウレタン・高反発素材など)の静音性の高いマットレスに替えると対策可能。特に高反発ウレタンやファイバー素材のマットレスは静音性に優れています。
▼マットレスについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
原因④ 金具の緩み

ベッドフレームの固定金具が緩んでいると、揺れのたびに音が鳴りやすいのが特徴です。ネジやボルトの緩みは使用中に少しずつ進行するため、知らないうちに軋みが発生しているケースもあります。
対策としては、定期的にドライバーなどで全てのネジやボルトを締め直しましょう。組み立て式ベッドの場合、半年に一度のメンテナンスを目安にするのがおすすめです。
 てぃも
てぃも金具の締め直しはもっとも効果的で手軽な方法です!工具があれば10分ほどで完了できるのもポイント。引越し後や購入から半年以上経ったタイミングで点検するとよいでしょう。
軋まないベッドを選ぶ6つのポイント
静音性の高いベッドを選ぶ際は、以下の6つの視点からフレーム構造や素材を確認しましょう。
- 軋みにくい素材のフレームを選ぶ
- 脚が太くて安定感のある構造を選ぶ
- 耐荷重が大きいモデルを選ぶ
- シンプルな構造で余計なパーツがないベッドを選ぶ
- 安価すぎるベッドは注意して選ぶ
- 背が低めのローベッドを検討・選ぶ
それぞれ詳しく解説します。
1:軋みにくい素材のフレームを選ぶ


頑丈な無垢材やスチールフレームは軋みにくく長持ちします。とくにしっかりとした加工が施された木製ベッドは、デザイン性と耐久性の両立が可能です。
無垢材は一本の木から切り出されているため、安定感があり接合部も少ない分、音が鳴りにくいというメリットがあります。スチール製は振動を吸収しやすい構造のものを選びましょう。
2:脚が太くて安定感のある構造を選ぶ
脚が細いベッドはぐらつきやすく、結果的に軋みやすくなります。重量が分散されやすい太い脚のフレームがおすすめです。
脚が太く重心の低いタイプは、安定性が高く横揺れを起こしにくいです。なかでも無垢材の四本脚タイプやフロア直置きタイプのベッドは音が出にくい傾向があります。
3:耐荷重が大きいモデルを選ぶ


耐荷重の目安は「体重 + 寝具重量の1.5倍以上」が理想。耐荷重の少ないベッドは早期劣化の原因になるため注意しましょう。
たとえば体重60キロの人で布団やマットレスが15キロなら、最低でも耐荷重110〜120キロ以上の商品が無難です。また、ふたりで使う場合は、倍の数値が必要になります。
4:シンプルな構造で余計なパーツがないベッドを選ぶ


棚や引き出しなどの付属パーツが多いと、金具が増えるので軋み音の原因に繋がります。極力シンプルな構造のベッドが理想です。
組み立て式の多機能ベッドは便利な反面、その分軋むリスクが高まります。ベッドフレーム本体と脚だけのシンプルな構造の商品は、緩みも起こりにくいため静音性が確保しやすいです。
5:安価すぎるベッドは注意して選ぶ


価格が安すぎる商品は、組み立ての精度や素材の品質が低い傾向にあります。とくに自分で組み立てる家具は、説明書通りにしっかり固定されていないと軋みの原因になりやすいです。
安価なベッドは部材が薄かったり、耐久性の検査が甘い場合もあります。購入時はレビューで「きしみ音がする」「揺れる」といったコメントがないかチェックしましょう。
6:背が低めのローベッドを検討・選ぶ


ローベッドは高さがない分、揺れが少なく安定性が高いのが特徴。視覚的にも圧迫感が少ないので、狭い部屋にもおすすめです。
床との距離が近いことで重心が低くなり、揺れの振動が伝わりにくくなります。ローベッドはフレームに厚みがあるものを選ぶと、軋みにくさが向上しやすいです。
▼ベッドの選び方について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
軋みにくいベッドフレームの種類と特徴
それぞれの生活スタイルや部屋に合った、軋みにくいベッドの種類を紹介します。
軋みにくいフレーム:すのこベッド


すのこベッドは、通気性が高く湿気対策も可能です。シンプルな構造で金具が少なく、軋みにくい設計が魅力。
桐や杉などの国産材を使ったすのこベッドは、耐久性に優れています。また、通気性の高さからカビやダニの繁殖も抑えやすいです。梅雨の時期や湿度が高い部屋にもおすすめ。



湿気が多い環境ではカビや歪みの原因になるため、除湿シートとの併用がおすすめです!私も部屋では実際に除湿シートを敷いています!
軋みにくいフレーム:大容量収納ベッド


跳ね上げ式や引き出し付きの収納ベッドは、収納物の重みで安定しやすいです。そのため、揺れや軋みを防ぎやすくなるのもポイント。
また、ベッド下のスペースを有効活用できるのも魅力です。収納物の重さがフレームの安定に寄与し、音がしにくいというメリットもあります。



大容量収納付きベッドは、季節ものの衣類や布団などの収納も兼ねたい人におすすめです!分厚い布団や毛布をベッド下に収納すれば、部屋のクローゼットを広く使えます。ファッション好きで服が多い人にとくにおすすめです。
軋みにくいフレーム:ローベッド(フロアベッド)


ローベッドは床に近い位置で設置されるため、揺れが伝わりにくいのが特徴。モダンでおしゃれなデザインも豊富です。
直置きタイプは脚がない分、構造が単純で音の発生源が少ないのもポイント。マットレスとの一体感も高く、寝返り時のきしみも気になりにくいです。



ローベッドは、賃貸物件やマンションなどで騒音対策したい人におすすめです。私は同棲時にステージタイプのローベッドを使用していました。耐久性のあるローベッドなら、カップルや夫婦で使用しても軋みが気になりにくいのが魅力です。
ベッドの軋みを防ぐ簡単な対策
ベッドの軋みを防ぐ簡単な対策は、以下がおすすめです。
- カーペットや防音マットを敷く
- マットレスの向きを定期的に変える
ひとつずつ紹介します。
カーペットや防音マットを敷く
カーペットや防音マットは床とフレームの摩擦音を防止し、音の響きを軽減しやすいです。また、耐震ジェルや滑り止めシートも併用できます。
さらに、厚みのあるジョイントマットやラグを使えば、床からの振動も吸収され、防音効果も高めやすいです。フローリングの部屋で使用する際は、床の傷も防ぎやすいのでおすすめです。
マットレスの向きを定期的に変える


同じ場所ばかりに体重がかかると、マットレスの劣化を早め軋みの原因に繋がります。マットレスの向きは、約3ヶ月おきのローテーションするのがおすすめ。
上下だけでなく表裏のローテーションも取り入れることで、マットレス全体の寿命を延ばしやすくなります。
軋まないベッドを販売するおすすめブランド
ここでは、静音性と耐久性に優れたベッドを販売しているブランドを紹介します。
おすすめブランド:WOODLIFE
WOODLIFEは集成材や突板ではなく、オークやチェリーなど本物の無垢材を採用しています。素材の質感や経年変化の味わいを大切にした頑丈な設計で、使い込むほど味が増しやすいです。デザインから製作まで自社工場で一貫して管理しており、短納期かつ高品質な仕上がりを実現しています。
また商品は日本の住宅事情に適したサイズ感と収納機能に配慮しており、コーナーラックやスリム家具など一人暮らしの部屋にもフィットしやすいです。健康塗料を使用しているので、小さな子どもやペットがいる家庭でも使いやすいのが特徴。
価格はやや高めではあるものの、一生ものの家具として素材や設計の質、アフターフォローなどのクオリティが魅力です。納期に余裕があり、頑丈なベッドをじっくりと選びたい本物志向の人におすすめ。
▼WOODLIFEについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
おすすめブランド:cacom (カコム)
cacom(カコム)はベッドやマットレスなどの寝具をはじめ、ソファやテーブルといった幅広い家具を取り扱うインテリアブランドです。オリジナル商品を数多く取り揃え、頑丈なベッドなどの寝具を低価格で購入できます。
強度や耐久性にこだわった商品も展開しているので、ベッドの買い替えを減らしたい人にもおすすめです。
▼cacom(カコム)について詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
おすすめブランド:暮らしのデザイン
暮らしのデザインは、家具全般の商品を取り扱うインテリアブランドです。頑丈ながら価格を抑えた商品が並び、一人暮らしやカップルが手にしやすい家具がそろいます。またチャットを通して、インテリアコーディネートのアドバイスを受けられるのもポイント。自分にあう寝具の選び方がわからない人にもおすすめのブランドです。
おすすめブランド:家具350
家具350は、実用性を考慮した商品が並ぶインテリアブランドです。トレンドにも敏感なブランドで、流行りのデザインを取り入れた頑丈な家具やインテリアを取り扱っています。独自の冷感寝具も展開しているので、暑い時期も安眠しやすい商品を選べるのが魅力です。
おすすめブランド:nerucoネルコンシェルジュ
nerucoネルコンシェルジュは「お客様の快適な眠りをコンシェルジュする」をテーマにした商品を取り揃えるブランドです。ベッドからマットレスまで寝具の種類が豊富に揃っています。多くの種類から自分にあう頑丈な商品を見つけたい方におすすめです。
▼nerucoネルコンシェルジュについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
おすすめブランド:BEDSTYLE
BEDSTYLEは、ベッド専門の通販サイトです。ベッドの種類やサイズの幅が広く、実用性の高い商品もそろっています。一人暮らしの人からファミリーまでどのような人でも、耐荷重が約200キロ以上のベッドを選べるのも魅力です。体格がよい人でも安眠しやすい頑丈な商品を選べます。
▼BEDSTYLEについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
おすすめブランド:モダンデコ
そのほかにも、多種多様な商品はデザインにもこだわっており、現代の住まいになじみやすいです。ベッドサイズはセミシングルからダブルまで展開。一人暮らしや同棲カップル、家族で使える寝具が取り入れやすいブランドです。
おすすめブランド:源ベッド
源ベッドは、日本製のベッドを取り扱うブランドです。ベッドからマットレスまで日本製にこだわっています。国産ひのきを使った商品は頑丈なつくりをしており、ひのき特有の香りも楽しめるのがポイント。森の中で寝ているようなリラックス感が得やすいのも魅力です。
おすすめブランド:MUTUKI
MUTUKIは、原料の直仕入れから自社生産・直販をしています。収納多めの家具や高さ調節可能なアイテムなど、使いやすさを重視した頑丈な実用設計が魅力です 。ほかブランドとも直接提携し、無駄な中間マージンを省くことで、高品質な家具をコスパ良く提供しています。
北欧・ナチュラル・ライトリュクス・韓国風・カントリーなど多彩なインテリアスタイルを展開しており、空間に馴染む洗練されたデザイン性が魅力です。
無垢材(オーク・チェリー・ウォールナット)や天然素材、竹製品などサステナブル志向が特徴です。耐久性の高い品質管理と塗料使用で「一生もの」家具を目指しています。千葉・船橋のイオンモールに実店舗も展開しています。
おすすめブランド:ENEN
ENENは、モジュラー方式で家具を長く自分らしく使い続けたい人にぴったりのブランドです。ソファ、チェア、テーブル、収納、ベッド、照明、雑貨、カーテンなどトータルに揃えられるのが特徴。天板や脚、フレームといったパーツを自由に組み合わせられる「KUUM(クーム)シリーズ」が代表作です。ライフスタイルやインテリアに合わせてカスタマイズでき、将来的にパーツ単位で買い足したり交換もできます。
公式サイトでは、AR・VRによる試用体験が可能。自由が丘や大阪・心斎橋に、実店舗とショールームを構えています。リアル店舗での触感確認も可能です。家具の修繕・パーツ交換・廃棄家具の回収に取り組みなど、環境へ配慮した取り組みもおこなっています。
そのほかにも、組み立てサービスや購入家具と同等サイズまでの回収サービスもあり、購入後のサポートまで充実度が高いのが魅力です。デザイン・機能・価格のバランスを大切にする方にとくにおすすめです。
軋まないベッドについてよくある質問(FAQ)
Q1. ベッドの軋み音をいますぐ止めるにはどうすればいいですか?
A. 金具を締め直し、ベッド下にマットやラグを敷くと即効性が期待できます。音が出始めた直後に対策すると、悪化を防ぎやすいです。
Q2. 軋み音の原因はベッドとマットレスどっちですか?
A. どちらの可能性もあるため、片方ずつ確認するのがおすすめです。とくにスプリングマットレスは、なかのコイルが軋み音を出している可能性もあります。ベッドフレームの上に布団を敷いて試すと、どちらに原因があるか確認しやすいです。
Q3. 賃貸でもベッドの音対策できますか?
A. カーペットを敷いたりローベッドを使用したりすれば、対策可能です。傷防止パッドもおすすめ。床に接する部分に家具用フェルトなどを貼るのも有効です。
まとめ
ベッドの軋みは放置すると睡眠の質を下げるだけでなく、近隣トラブルにも繋がってしまう可能性があります。深夜や早朝にベッドの音が響くと、自分だけでなく他人の生活リズムにも悪影響を与えてしまうかもしれません。
ベッドを選ぶ際は「静音」「耐久性」「構造」の3点を意識し、自宅に合った軋まないベッドを見つけましょう。