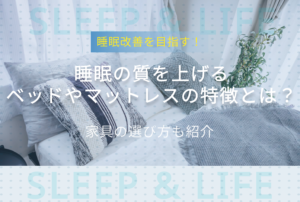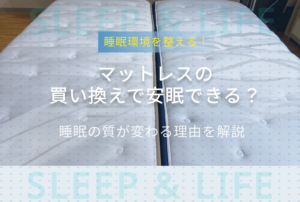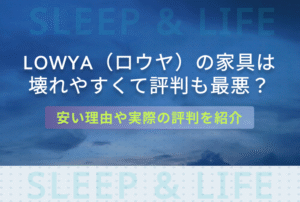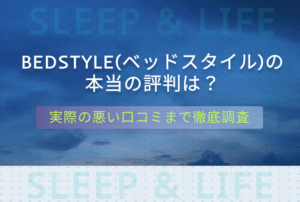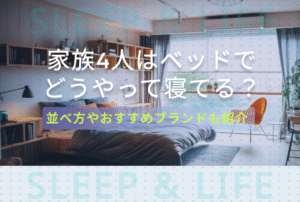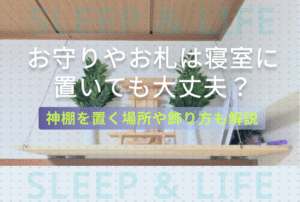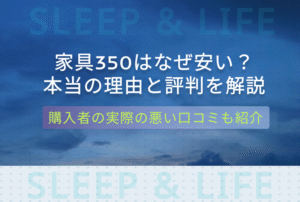ベッドの買い替えを検討している人のなかには、安眠が目指せる商品を選びたい人もいますよね。どこのブランドを選べばよいのかが気になるのはもちろん、疲れが取れるベッドの特徴を知りたい人もいるかもしれません。
そこで本記事では、安眠につながりやすいベッドを展開しているブランドをランキングで紹介します。さらに、疲れが取れやすいベッドの特徴やマットレスの選び方のポイントも解説するので、安眠を目指したい人はぜひ参考にしてみてください!
 てぃも
てぃも寝具の買い替えが必要なく、そのまますぐに使える疲れが取りやすいおすすめ商品はこちら!
安眠につながりやすいベッドのおすすめブランドランキングTOP12
まずは、疲れが取れて安眠につながりやすいベッドやマットレスを展開するおすすめブランドを、ランキングでみていきましょう。
ブランドランキング1位:エムリリー
低反発でも高反発でもない独自の新素材を使用して二層構造にすることで、優しい反発力で理想的な寝姿勢で疲れを取りやすいです。部活をしている子どもやスポーツをしている人、毎日の仕事や家事でストレスや疲れが溜まって疲労が取りづらくなっている人におすすめ。
また、現在使用している寝具の上にそのまま重ねるだけで使用できるので、既存の寝具にあわせて使える商品を探している人にも向いています。睡眠に悩んでいて、疲れが取れる寝具をまずは試してみたい人におすすめのブランドです。



いま部屋で使用している既存の寝具と一緒に使えるのが嬉しいポイントです!試してみてから体に合う合わないがあった際も、家族で合う人が使うなどの調整もしやすいです!
▼エムリリーについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
ブランドランキング2位:シェーンベルグ
素材によって特性がさまざまなので、保温性・弾力性・吸湿性・発散性・通気性・耐久性など、一人ひとりの疲れの取り方や安眠のための好みにあわせやすいオーダーメイド商品です。疲れをとることを優先に寝具を選びたい人や、自分用だけでなく恋人や家族にワンランク上の快眠用のプレゼントを探している人にもおすすめ。
シェーンベルグの商品レビューでは「使い続けていると、肩が軽くなってくるのが分かった」といったコメントも見つかりました。ベッドやマットレスだけでなく、まずは枕を変えるのも疲れを取るための方法です。
ブランドランキング3位:cacom (カコム)
cacom(カコム)はベッドやマットレスなどの寝具をはじめ、ソファやテーブルといった幅広い家具を取り扱うインテリアブランドです。オリジナル商品を数多く取り揃え、安眠できる寝具を低価格で購入できます。
強度や耐久性にこだわった商品も展開しているので、ベッドの買い替えを減らしたい人にもおすすめです。
ブランドランキング4位:WOODLIFE
WOODLIFEは集成材や突板ではなく、オークやチェリーなど本物の無垢材を採用しています。素材の質感や経年変化の味わいを大切にした設計で、使い込むほど味が増しやすいです。デザインから製作まで自社工場で一貫して管理しており、短納期かつ高品質な仕上がりを実現しています。
また商品は日本の住宅事情に適したサイズ感と収納機能に配慮しており、コーナーラックやスリム家具など一人暮らしの部屋にもフィットしやすいです。健康塗料を使用しているので、小さな子どもやペットがいる家庭でも使いやすいのが特徴。
価格はやや高めではあるものの、一生ものの家具として素材や設計の質、アフターフォローなどのクオリティが魅力です。納期に余裕があり、じっくりと選びたい本物志向の人におすすめ。
▼WOODLIFEについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
ブランドランキング5位:暮らしのデザイン
暮らしのデザインは、家具全般の商品を取り扱うインテリアブランドです。価格を抑えた商品が並び、一人暮らしやカップルが手にしやすい家具がそろいます。またチャットを通して、インテリアコーディネートのアドバイスを受けられるのもポイント。自分にあう寝具の選び方がわからない人にもおすすめのブランドです。
ブランドランキング6位:家具350
家具350は、実用性を考慮した商品が並ぶインテリアブランドです。トレンドにも敏感なブランドで、流行りのデザインを取り入れた家具やインテリアを取り扱っています。独自の冷感寝具も展開しているので、暑い時期も安眠しやすい商品を選べるのが魅力です。
ブランドランキング7位:nerucoネルコンシェルジュ
nerucoネルコンシェルジュは「お客様の快適な眠りをコンシェルジュする」をテーマにした商品を取り揃えるブランドです。ベッドからマットレスまで寝具の種類が豊富に揃っています。多くの種類から自分にあう安眠しやすい商品を見つけたい方におすすめです。
▼nerucoネルコンシェルジュについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
ブランドランキング8位:BEDSTYLE
BEDSTYLEは、ベッド専門の通販サイトです。ベッドの種類やサイズの幅が広く、実用性の高い商品もそろっています。耐荷重が約200キロ以上のベッドを選べるのも魅力です。体格がよい人でも安眠しやすい商品を選べます。
▼BEDSTYLEについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめです!
ブランドランキング9位:モダンデコ
そのほかにも、多種多様な商品はデザインにもこだわっており、現代の住まいになじみやすいです。ベッドサイズはセミシングルからダブルまで展開。一人暮らしや同棲カップル、家族で使える寝具が取り入れやすいブランドです。
ブランドランキング10位:源ベッド
源ベッドは、日本製のベッドを取り扱うブランドです。ベッドからマットレスまで日本製にこだわっています。国産ひのきを使った商品は頑丈なつくりをしており、ひのき特有の香りも楽しめるのがポイント。森の中で寝ているようなリラックス感が得やすいのも魅力です。
ブランドランキング11位:VENUS BED


VENUS BEDは、6000通りの組み合わせから好みと寝具が選べるブランドです。50年以上の歴史を持っており、ベッドやマットレスはもちろん、シーツや枕といった寝具までそろいます。商品数が多いので、自分の体格にあう安眠しやすいベッドが選べるのがポイントです。
ブランドランキング12位:エアリゾーム


エアリゾームは、寝具やダイニングなどの大型家具から、部屋のアクセントになるインテリア雑貨まで取り揃えるブランドです。コンパクトな商品も多く取り扱っているので、狭い部屋にも置きやすい
コンパクトな商品も多く扱い、新生活をスタートしたい人にもおすすめ。ベッドはシンプルさにこだわり、置く部屋を選びにくいのが魅力です。
▼安眠できる安いベッドについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
疲れが取れるベッドの特徴
疲れが取れやすいベッドの特徴は、以下の3つがあります。
- 頑丈な構造
- 耐荷重が大きい
- 寝床の位置が低い
それぞれの特徴をみていきましょう。
疲れが取れるベッドの特徴①頑丈な構造


疲れが取れやすいベッドは、頑丈な構造をしているのがポイントです。ベッドは種類によって、使用する素材や構造が異なります。
脚やフレームが太いベッドは、頑丈な構造をしているのがポイント。ベッドの構造がしっかりしていると、横揺れやきしみを防ぎやすくなります。睡眠を妨げにくいため、日中に蓄積した疲れも取れやすくなるかもしれません。
また、ひのきや桐は木材のなかでも比較的頑丈な素材をしています。ひのきは木の香りも感じられるので、安眠にもつながりやすいです(※)。
※参照:森の香りを科学する
▼頑丈なベッドについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
疲れが取れるベッドの特徴②耐荷重が大きい


疲れが取れるベッドには、耐荷重が大きい特徴もあります。耐荷重とは、ベッドが耐えられる最大の重さのことです。ベッドに乗せるマットレスと体重の合計が耐荷重を超えると破損につながる可能性があります。
耐荷重が大きいと、複数人で使用しても寝返りの際に振動が相手に伝わりにくかったりきしみ音が起きにくかったりするのがポイント。お互いの睡眠を妨げにくいので、疲れが取れやすい傾向にあります。
▼ギシギシ軋まないベッドについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
疲れが取れるベッドの特徴③寝床の位置が低い


寝床の位置が低い点も、疲れが取れるベッドの特徴です。寝床の位置が低いベッドには、ローベッドやフロアベッド、ステージベッドなどがあります。フレームの底全体が床に接地する商品であれば、横揺れやきしみも起きにくいでしょう。
一方、寝床の位置が高いベッドは安定感に劣る可能性があります。とくに、ロフトベッドは脚が長いのがポイント。横揺れやきしみに敏感な人にとっては、睡眠が取りにくいかもしれません。疲れが取れやすいベッドを選ぶなら、高さを考慮することも重要です。
▼疲れを取るために睡眠の質について詳しく知りたい人は、以下の記事もおすすめです。
安眠につながりやすいベッドマットレスの選び方


安眠を求める場合は、ベッドフレームに組み合わせるマットレスにこだわるのも重要です。
次に、マットレスの選び方をみていきましょう。
マットレスの選び方①体にあう硬さを考慮する


マットレス選びは、体にあう硬さを考慮するのがポイントです。マットレスの硬さが体にあっていないと、寝返りがしづらかったり体の一部に負荷がかかったりしてうまく睡眠が取れない可能性があります。
自分にあう硬さを見極めるには、体格にあわせたマットレス選びをするのが重要です。体格がよい人であれば、硬めのマットレスを選ぶのがポイント。沈み込みすぎないため、体圧も分散しやすくなります。
一方、体重が軽い人は柔らかめのマットレスを選ぶのがおすすめです。体にマットレスがフィットしやすくなり、適切な寝姿勢を保ちやすくなります。



私はマットレスが硬すぎても柔らかすぎてもうまく寝付けないので、自分の体に合う商品かどうかは、フィット性を重視して選んでいます。
▼マットレスについて詳しく知りたい人は、こちらの記事もおすすめ!
マットレスの選び方②中材にこだわる


マットレス選びは、中材にこだわるのも重要です。マットレスはスプリングタイプのコイルマットレスとコイルを使用しないマットレスがあります。硬さに加えて、マットレスの中身にこだわることで自分にあったマットレスを選びやすくなるかもしれません。
中材にコイルを使用するマットレスは、各コイルが点で体を支えてくれるため、体圧分散がしやすい特徴があります。しかしコイルが伸縮する際に音が生じるケースがあるでしょう。音に敏感な人にとっては、雑音に感じる可能性があります。
一方、ウレタンやファイバーを使用したマットレスは通気性に優れているのがポイント。体のラインに沿ってマットレスがフィットしやすいので、体圧分散もしやすいです。ただし、コイルマットレスと比べて耐久性が低い傾向にあります。へたりやすい場合もあり、買い替え頻度が多くなるかもしれません。
それぞれの特徴を考慮したうえで、自分にあったマットレス選びをすると安眠につながりやすくなります。
安眠できるベッドの工夫
安眠を目指すなら、ベッドパットを併用するのがおすすめです。ベッドパットとは、マットレスに付着する汚れを防いだり寝心地を調整したりといった役割がある寝具を指します。通気性が劣る際や寝心地が悪い際に役立つのが特徴です。
使用中のマットレスに不快感を覚える際も、ベッドパットを組み合わせれば改善できるかもしれません。また季節にあわせてベッドパットを変えると、季節的な不快感も改善しやすくなります。
まとめ
本記事では、安眠につながりやすいおすすめのベッドを展開するブランドをランキングで紹介しました。日中に蓄積した疲れを取るには、頑丈構造で耐荷重の大きいベッドを選ぶのがおすすめです。マットレスの選び方のポイントも解説したので、安眠を目指したい人はぜひ参考にしてみてくださいね。